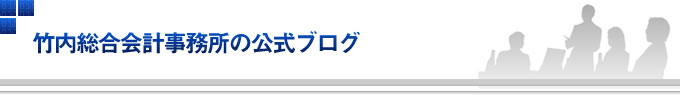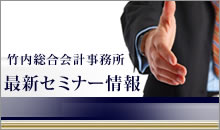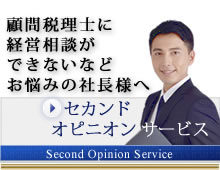◆経営計画の運用
第3回のコラムで「経営計画書は作成して終わりではありません。運用することこそが経営者の最も重要な仕事であり、これを活用し、会社の業績を上げていくことが最終目的である」といった話をしました。
経営計画では、経営ビジョンに基づく中期の売上・利益の目標数字作りを行います。それを年度ごとの短期の目標計画にまで落とし込み、1年間の中での季節変動などを考えた上で毎月の計画に落とし込みます。その月次計画目標が達成できているのか否かを確認するのが予実管理にあたります。
実績は、月次決算でその数字を確認することができますので、予(計画)に対してどうであったのかを比べてみることが重要です。特にその達成度や差異の確認は最低限しなければなりません。
◆PDCAのマネジメントサイクル
予実管理を発展させるとPDCAのマネジメントサイクルを作ることになります。
“P”とはPLAN(計画)、“D”とはDO(実行)、“C”とはCHECK(検証)、“A”とは、ACTION(修正実行)のことです。
経営計画を作成することがPLANにあたります。その目標計画を達成するための活動をすることがDOにあたります。実績の結果を検証する際に月次決算データをCHECKすることになり、そこで問題点・課題を見つけどのように改善していけばいいのかを考え次のACTIONを起こすことになります。予実は計画・実績の確認だけで終わらせていたらただの確認作業でしかありません。行動したことの反省や検証があり、それを次の改善に活かすことこそが予実管理の本来目指すところになります。
◆予実管理は月次会議で行う
計画数字の達成はもちろん全員で共通した目標を持ち、取組むことが必要です。そのため、社員が参加した月次会議での予実確認が有効です。月次会議は、月初か月末に行い下記のスケジュールで進行させます。
①前月の計画の確認
②前月の実績の確認
※個人の予実績確認も併せておこなう
③取組み上での反省等による検証
④今後、どのように改善し、取り組んでいくのか
⑤今月の(修正)計画の確認
PDCAのところでも強調したように、③の取組み上、活動においての反省をして④のそれを改善していくことが会議の目的です。しかし、実際の運用上は反省をするだけではなく、成功事例の共有や上手くいったことに対して評価をするなど、社員のやる気やモチベーションを上げるような会議にすることがあるべき月次会議の姿といえます。
◆個人目標の重要性
月次会議の中で『個人の予実績確認を併せて行う』と記しましたが、会社の目標数字だけではなく個人別の目標を持たせることはとても重要なことです。
社員にとって最もわかりやすい目標は売上の目標数字です。年間の目標数字を月次にするのはもちろんのことですが、キャリアによってはもっと短い期間で設定することも一案です。
ただ、あまり細かな目標を設定すると押し付けられたものとなってしまう可能性が出てきて、社員のモチベーションにも悪影響を及ぼしてしまうことになりかねません。
目標の設定においては、経営者の定めるもの(高くなりがち)と社員が設定するもの(低くなりがち)の両方の意見や考えを聞いたうえで、最終的に目指すものを決定すべきです。その目標数字を上方に持っていくためには、経営者はその理由を明確にし、その社員への期待度を示すことが有効です。理由を理解し、期待をされた社員は、達成が難しい目標でも「やる気」をもってトライすることができます。同じ目標を与えることにおいても、その目標の設定のやり方やその意味の与え方で活きた目標にすることができることを経営者は認識しておくべきです。